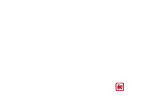【鮨かの 酒蔵訪問記】滋賀県東近江市。のどかな田園風景の中にある増本藤兵衛酒造場を訪れる!
造り手の想いに触れる酒蔵訪問記録。Part6。
お米の旨味溢れる藤兵衛は、家族の暮らしの中で作られていた!
令和7年10月。東京にもようやく秋がやって来た頃、滋賀県東近江市 琵琶湖の東方面に蔵を構える増本酒造場を訪れてきました。
増本酒造場の創業は明治初期。地元では〝薄桜〟という銘柄の日本酒が人気です。
〜逢う友よ 見せてやりたい 薄桜〜
これは、増本さんの名刺に書いてあった句です。
あるお客さんが、〝薄桜〟を手土産に持って行った所、その友達に大変喜ばれた為、店頭で詠んだ句だそうです。
手にすると笑顔がこぼれる。そんなお酒作りを続けたいという想いで、ボトルのラベルと名刺に記載しているそう。
関東の飲食店では滅多にお目にかかれない、お米の旨味溢れる近江藤兵衛はどんな場所で、どんな人によって作られているのか。
鮨かの酒蔵訪問記 近江藤兵衛編の始まりです!
もくじ
増本酒造場のある東近江はこんなトコ!
増本酒造場へは、中心部の大津市内からは車で1時間ほどかかります。
琵琶湖のほど近く。周辺に広がる田園風景に馴染む様に、その蔵はあります。
この辺りは高い建物が無いので、視界がとても広く、日照時間が長い事が予想されます。
訪れた時は綺麗な夕暮れが広がっていました。思わず背伸びしたくなりますね。

周辺には観光名所の彦根城があります。
安土城跡などもある歴史ある土地です。
東には鈴鹿山脈。そこから流れる水が仕込み水です。
近江藤兵衛はこんな人たちによって作られていた!

当主の5代目増本藤兵衛(55才)さん。
このお名前は、先祖代々継承されているお名前です。令和7年、先代がお亡くなりになり現当主が〝藤兵衛〟の名前を襲名されました。
鮨かのでは、その名前を冠した〝近江藤兵衛〟シリーズを提供しております。
こちらのお酒は、米の旨味を存分に感じられるお酒。特に燗をする事で更に味わいが引き出されます。
これからの季節は、旨味の強い料理、煮物などと合わせて楽しむと、より美味しく感じる事が出来ると思います。

増本酒造場の大きな特徴として、おウチの裏に日本酒の仕込み場が有る事が挙げられます。
〝くつろぎ部屋の隣に仕込み場〟です。
生活の一部に日本酒造りがある。正にそれを地でゆく日本酒蔵です。

大きな日本酒タンクは部屋のうら。
生活の一部に日本酒作りがある事で、その日の気温や湿気を文字通り肌で感じる事が出来るのだと思います。

こちらは麹室。前室もあり大き目な麹室。デリケートで神聖な部屋です。
地元のお米を原材料として、仕込み水はおウチにある鈴鹿山系の井戸水。それを住人が醸す。
存分に滋賀を感じられる日本酒。それが近江藤兵衛なのです。

西方向にある琵琶湖からは気持ちの良い風が蔵の中を吹き抜けます。
夏はこの場所に椅子を持ってきて涼む特等席なんだとか。この日も夕焼けがとても綺麗でした。
鮨かので飲める近江藤兵衛はコレ!

鮨かのでは現在、〝近江藤兵衛 純米酒 中汲み〟をラインナップしています。
使用米は滋賀産銀吹雪。スペックは、アルコール17度 日本酒度+7 酸度1.6となっています。
口に含んでみると、酸味も感じられる蜜の様な力強い旨味が広がり、その後にくる辛味が喉越しを良くします。
また、燗する事で、甘みは柔らかく旨味がほっこり。ホッとする味わいになる旨味豊かな食中酒です。
原料米の銀吹雪は、夏の暑さに弱いそうで、現在、新たに品種を改良しているそうです。
銀吹雪は、ひょっとすると数年後に無くなっている可能性もあります。
のどかな東近江で作られた、味わいがギュッと詰まった藤兵衛は、ゆったりした時間の中で丁寧に作られております。
そんな風景を思い浮かべながら飲みたい日本酒ですね!