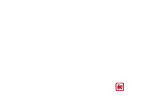【鮨かの 酒蔵訪問記】宮城県栗原市。田んぼの中の蔵。金の井酒造を訪れる!
造り手の想いに触れる酒蔵訪問記。Part5。
食事に優しく寄り添う綿屋は、広大な田んぼの中で造られていた!
令和7年9月。少しだけ秋の気配を感じられる様になった頃。宮城県栗原市にて、純米酒〝綿屋〟を醸す〝金の井酒造〟を訪問して来ました。
【食中酒を超えた食仲酒へ】
これをテーマに造られる綿屋は、単体で飲むよりも、食事と合わせる事で更に美味しく感じられる日本酒です。
食事に寄り添い、飲み疲れしないスッキリとした味わいの綿屋は、鮨との相性もバッチリ。
鮨かのでの定番酒となっています。
優しい味わいを持つ綿屋は、どんな所でどんな人達の想いによって造られているのか。
それを体験するため、栗原市一追を訪れて来ました。
懐かしの栗原市訪問記

金の井酒造は、かつて炭坑があった頃、そこまで続く子安街道沿いに有りました。
街道という名前が付いていますが、現在はなんでもない田舎道。
周辺の建物を見てみると、小さな民宿や食堂、ガソリンスタンドの跡などが見られます。
かつては賑やかな頃もあった事が想像出来ます。
金の井酒造がある宮城県栗原市はこんな所!

金の井酒造は、宮城県北西部。岩手県や秋田県のほど近くの栗原市一追にあります。
蔵の周辺に広がるのは、夏にはどこまでも続く緑。秋には黄金色の絨毯の様に広がる広大な田んぼ。
昆虫や小動物が元気に暮らす自然豊かなところ。
東北らしいのんびりとした雰囲気を感じます。

遥か先まで広がる田んぼ。そこでは〝ひとめぼれ〟や〝美山錦〟など。食用米や酒米が大切に育てられていました。
日本人としての遺伝子なのでしょうか。田んぼを眺めていると、なんだか落ち着きますね。
仕込み水として使われる小僧山水

金の井酒造が造る日本酒の一つの特徴に、小僧山水と呼ばれる山の清水をふんだんに使用している事があります。
洗米、仕込み、洗浄。その他全ての仕事で、この小僧山水が贅沢に使用しているのです。
入り口には鳥居があり、神社がある神聖な場所です。禊も行われる清らかな水です。
四季を通して安定した温度の清水。
味わってみると、微かなトロみと甘味を感じました。硬度は中軟水。
宮城県外からも、わざわざこの水を汲みに来る人も居るそうです。
歴史を感じる蔵の中。

お酒造りの作業を簡単にまとめると
①精米→洗米と浸水→蒸し。
②酒母造り。(酛と呼ばれます)
③麹造り
①〜③を合わせて醪(もろみ)となる。
それを濾して瓶づめ。貯蔵になります。

蔵内を見学させて頂きましたが、歴史と空気になんだか緊張してしまいました。

敷地内には、昔JAで使われていた石室を改修したとても大きな冷蔵庫があります。
一升瓶に詰められた日本酒は、大きな冷蔵庫の中で熟成され、味を調整。

数ヶ月寝かせられたお酒から、2~3年。趣味で8年以上寝かせたものまで。
大きな冷蔵庫の中は一升瓶でいっぱいです。

もちろんラベル貼りも手作業。曲がらない様にラベルを貼る。大切な仕事ですね!
この時は、金の井酒造のご近所にある〝川口納豆〟とのコラボ日本酒のラベル貼りで大忙しでした。

案内してくれた五代目蔵元 華子ちゃん。ありがとうございました!
スキーの季節になったら一緒に滑りましょうね!
実は、ここ宮城県栗原市は、鮨かのの先代の出身地なのです。
そんな個人的な思い入れもあり、綿屋は私にとって少し特別なものとなっております。
鮨かので飲める綿屋はこれ!
現在、鮨かのでは特別純米酒 幸之助院殿をナインナップしています。
酒粕を肥料に混ぜて飼育した牛の有機肥料を用い、栽培された宮城県栗原産の特別なひとめぼれが原料米になっています。
ちなみに〝幸之助〟さんは、この特別なお米の生産者さんのご先祖で、〝院殿〟は位の高い人の戒名だそうです。
先代に深い敬意を払った日本酒という事です!

スペックは、日本酒度+1。酸度1.9。精米歩合55%。アルコール度15度。となっています。
冷やして飲むと、スッキリと食事に寄り添い、温めて飲むと、軽やかな優しい旨味が広がります。
綿屋の凄いところは、お水をおつまみにしても美味しい。というところ。
お水が甘くなり、綿屋の味わいもふっくらと増す。
なんだか魔法の様です。
ぜひ鮨と合わせて、その魅力を感じてみて下さいね!